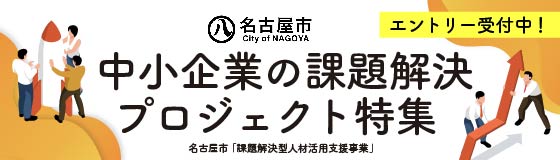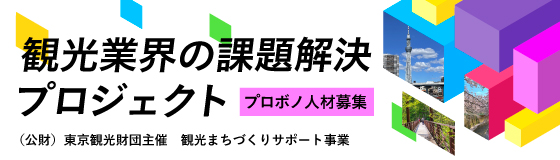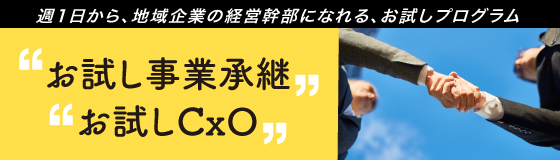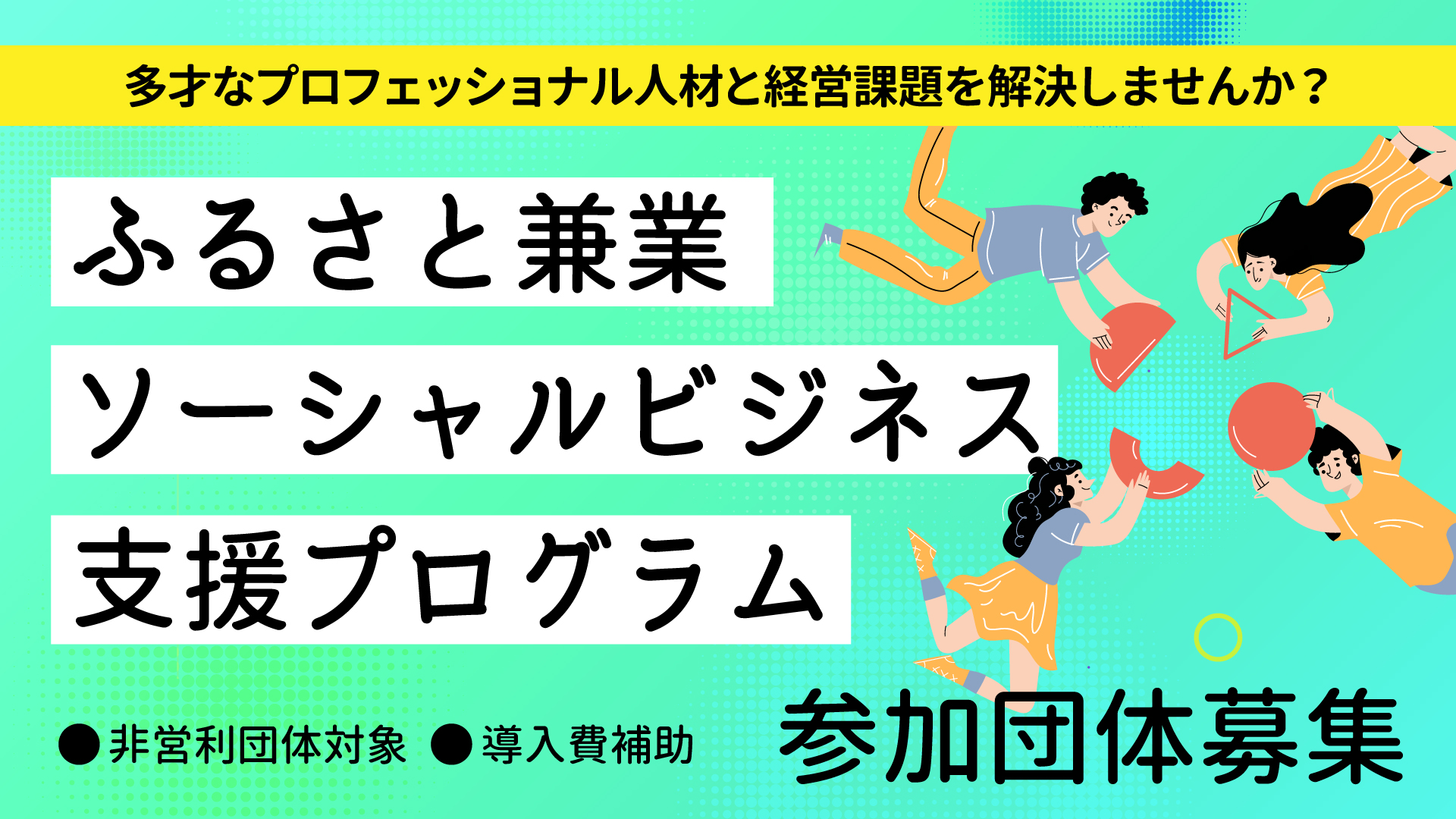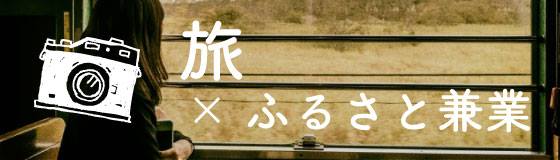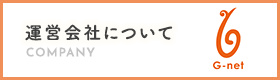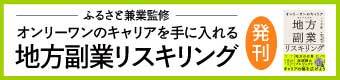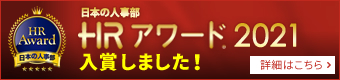【広報・魅力発信】日本屈指の農業大国「東三河地域」で、農業というキャリアの選択肢と学びの場を提供する
 1か月前
1か月前 566 view
566 view
募集は終了しました

プロジェクトについて
■㓛農支援会とは
㓛農支援会は、平成26年(2014年)に、農業を総合的に支援するイノチオグループ(本社:愛知県豊橋市)の二代目代表、石黒㓛三氏が「日本の農業者の減少と、新規就農者の自立の難しさ」という課題解消に役立ちたいとの想いから設立した農業経営者を育成する公益財団法人です。
「就農」には、農業の技術の習得はもちろんですが、資金の確保・農地の取得・販路開拓など多様な業務を進める力が必要になっており、農業を志す方たちにとっては、大きなハードルでもあります。
それらを支援・サポートするのが私たちの役割でもあります。
■地域の特徴や魅力
東三河地域は、愛知県の東南部に位置し、温暖な気候と豊川用水の恩恵に加え、交通網の整備によって、キャベツやブロッコリー、電照菊、トマト、大葉など、人々の身近な農作物が多種多様育てられている日本屈指の農業大国でもあります。
その中でも㓛農支援会のある豊橋市は全国的に見ても農業が盛んな地域で、市町村ごとの農業産出額(農業粗生産額)では昭和42年から平成16年の統計まで全国第1位となっており、全国の市町村合併が進んだ現在でも全国トップクラスの産地となっています。さらに隣接する豊川市、田原市なども加えた東三河エリアは国内屈指の園芸地帯です。
また、㓛農支援会を支える協力企業が多数立地し、持続可能な農業モデルの実現へ向けて、スマート農業などロボット技術やICTを活用した新たな農業に接する機会にも恵まれ、農業の学びの場として、大変適した地域といえます。
■抱えている課題
現在、㓛農支援会では、「農業を学びたいがゼロからのスタートで悩んでいる」、「農業経営を学んでみたい」
といった人々に向けて、以下の2種類のコースを展開しています。
①基礎研修(4~6カ月)
農業で自立するために必要な農作物を栽培する力、販売する力を育成
②本研修(1~1.5年)
農作物を栽培する力、販売する力をベースに、農業経営の力を育成
研修生は、主に民間や自治体が主催する就農フェアへの出展にて募集をしていますが、現在は年に2~3名の参加にとどまっています。
この東三河地域という農業大国で、さらに多くの方に研修を受けてほしいと思っていますが、「就農フェア」以外に、関心層と接点を設ける手段に取り組むには、知見も人手も足りず、なかなか挑戦できていないのが現状です。
また、農業へのチャレンジの魅力や、東三河の地域で学ぶことの価値が、まだ伝えきれていないのではないかとも考えています。
■兼業者と一緒に取り組みたいこと
今回、兼業者の方と一緒に取り組みたいことは、「㓛農支援会が主催する研修プログラムへの参加者増加のためのアプローチ方法を検証・試行錯誤すること」です。
誰に向けてどんなアプローチ方法が効果的なのか?ターゲット層を明確にしたうえで、現在活用している広報媒体やイベントの他に適切な媒体や、イベント等の活用の検討などをおこないたいと考えています。
また、将来的には社内のスタッフが本取り組みを進められることが理想的と考えています。一緒に取り組んできたことが、今後も引き続き進められるためのノウハウの蓄積(必要であればマニュアルの作成や、社内に残していく環境整備)も、人材の方には相談、お願いできると嬉しいです。

プロジェクトが目指すこと
■農業界にある背景
農業就業人口は年々減少しています。
その背景には、農業従事者の高齢化、現場における厳しい労働環境や、農業が知識や経験に基づく高い熟練性を必要とすることが考えられます。そのため、若者の就農への新規参入がなかなか進まないのが現状でもあります。
一方で、生活に直結する「仕事」として、関心ある層は一定数いることが確かです。そこから「就農」に繋がる導線をつくることの難しさも恐らく課題としてあげられます。
■「農業」というキャリアの多様さと幅広さへの理解とチャレンジ
また、「農業」といっても、農作物の栽培を習得することだけではないというギャップも、就農を考えている方々にとって大きなハードルやギャップとなっているかもしれません。
大規模な農業ファームに就職しない限りは、その農作物を扱う経営者であることが求められます。
そのため、経営そのものの知識や経験、伝統的な生産方法にとられない新たな試みを取り入れたり、販売するためにマーケティングやブランディングを考える力が必要となり、習得するスキルや技術は多岐にわたります。
そのような背景もあり、功農支援会では、農作物の栽培だけでなく、農業経営力の体得や農産物の販売までを研修に含めており、農業が継続して続けられるような教育体制モデルをブラッシュアップし続けています。

農業大国であるこの東三河地域では、一般的に消費される農作物を主要に大規模農業がおこなわれています。
しかし、農業の未来を担うのは決して大規模農業だけではありません。
大規模農業は、初期投資や土地の確保など、新規参入が難しいことが多く、これから農業を始める方たちは、まずは小規模農業が多いです。
ただし、小規模農業は、多品目栽培、高付加価値のある農産物を育み販売する経営スキルがより必要になってきます。
㓛農支援会では、施設園芸を軸として、多様な栽培方法で、多種多様な農産物を育てられる日本有数の環境を整えています。
そのような環境が、研修生にとって「選ばれる」強みになることは間違いありません。
現在、研修を受けている実習生の話を聞くと、「農業就業」や「特定の農産物を育てること」に強い想いがあったというよりは、
移住や、ふとした時の農業への関心をきっかけに挑戦を決意し、基礎的な知識やスキルを丁寧に受けられ、幅広く多様な農産物や栽培方法を試すことができる功農支援会の研修内容に魅力を感じた方が多いです。
それらの強みを引き出し、具体的な施策として実行まで落とし込んでいくことが、今後の農業界を担う人材育成の入口をつくる一歩になるのではないでしょうか。
プロジェクトパートナー
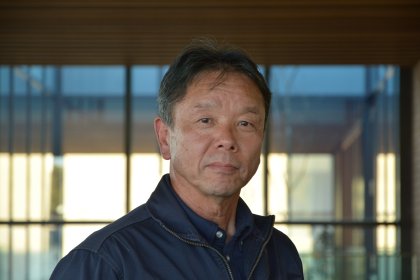
公益財団法人㓛農支援会
農場長 山口健
私たち㓛農支援会は、次世代の農業経営者を育成しています。
私たちの活動に賛同していただける方で、研修を希望される方に当農場の魅力をしっかり伝えていただけるスキルをお持ちの方は、是非エントリーお願いします。
農業の未来を一緒に考えていきましょう。
募集要項
- 仕事内容
- 【STEP1】プロジェクト・企業理解(1ヶ月)
・まずは、田原市の農業の課題、㓛農支援会の取り組みを理解する
・現地へ訪問し、実際の現場や、経営者・担当者の想いを知る
【STEP2】ターゲット層と方針の決定/広報媒体や施策の洗い出し(1ヶ月~2ヶ月)
・ターゲット層決定(ペルソナ決定)と、他の研修プログラムリサーチなどヒントを得る
・その他の広報媒体や、施策を洗い出しする
【STEP3】新たな広報施策準備スタート(2ヶ月~)
・(a)新たな広報媒体の活用:市場調査や基本設定、導線の確認や、戦略設計など
(b)自社での活動媒体(SNSなど):戦略・行動計画をたてる
・いずれにしても必要な資料の作成をおこなう
【STEP4】試行錯誤を繰り返す+ノウハウを残すための準備(3~4ヶ月)
・(a)新たな広報媒体の活用:広報媒体開設までの準備と運営と、開設後の試行錯誤
・ (b)自社での活動媒体(SNSなど):自社の取り組みであれば試行錯誤
→ その後、試行錯誤した本プロジェクトの運営が、現地スタッフで可能な状況に考案していただけるようなマニュアル作成または引き継ぎ、環境提案などをしていただけると嬉しいです!
- 期待する成果
- ・㓛農支援会の研修のエントリー率が高くなる
・㓛農支援会の取り組みを理解し、就農関心層であるターゲットに㓛農支援会の良さを伝え、関心をもってもらえること
・農業の担い手になり得る材のニーズに合った媒体やコンテンツの調査や企画、試行錯誤ができる
・SNSなどをあらたな取り組みの提案と、継続性があるノウハウの展開 - 得られる経験
- ・ターゲットのニーズに合ったものを新たに作り出す経験
・プロジェクトの軸としてリーダーシップを発揮する経験
・次世代の農業の発展に貢献できる - 対象となる人
- ・アイデア立案だけでなく、共に実務としても試行錯誤してくださる人
・既存の資源やリソース、経営者や担当者の想いに共感いただける人
・日本の農業界を応援したい人
・ロマンとそろばんの考えを持っている人
【歓迎スキル】
・マーケティング、ブランディング経験のある人
・SNSやwebプロモーションの経験のある人
・農産物に関わる仕事に従事されていた人 - 活動条件
- ▼活動予定期間
2025年3月~6月(そのうち3~4ヶ月程度)
※事業終了後も引き続き関わっていただける方、大歓迎です!
▼稼働時間
週4~8時間ほど(週1程度)
▼活動方法
オンラインが基本
ただし、スタート時は豊橋または田原市にお越しいただきます
▼その他
2週間または1週間に1回程度のオンラインミーティングに参加できること
※オンライン打ち合わせは担当者やプロジェクトメンバーの隙間時間によって、日時を調整します。
▼選考方法に関して
選考スケジュールは下記のようになりますので、
必ずご確認のうえ、エントリーいただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
◆エントリー〆切日:第1次〆切3月22日(土)
◆選考スケジュール:
【1】書類選考:エントリー後、〆切日までに随時実施
※そのため、必ず志望動機等は記入ください。選考の参考にさせていただきます。
【2】企業面接:書類選考後、随時
【3】合否通知:決定次第連絡がございます。面接の際に目安日程をお伝えします
◆書類選考の結果通知について
・エントリー後、随時書類選考させていただき、書類選考結果のご連絡をいたします。
・各企業プロジェクトエントリー〆切日以降、1週間経過しても返信がない場合は、大変恐縮ですがご連絡いただけますと幸いです。
・応募多数の場合、通知までにお時間をいただく可能性がございます。(その際はご連絡いたします。)
<書類選考について>
◎マイページの記載内容(ご経歴、スキル、経験など)
◎エントリー時の志望動機などの内容
上記2点で書類選考をさせていただきますので、十分にご記入いただきますようお願いいたします。
※応募状況により、選考方法の順番や要する期間が変わります。 - 報酬/待遇
- ・兼業・プロボノ、募集しています。
※兼業者の場合は、3万円/月(税込)
・プロジェクトに関する経費については企業側で負担します。 - 活動場所
- 【住所】愛知県豊橋市西赤沢町万場261
スタート時はぜひ現地にお越しいただいて農場を実際に拝見いただいたり、研修生や担当者とコミュニケーションをとっていただき、課題や魅力を実感いただけますと幸いです。
その後は基本オンラインにて実施となります。 - 募集終了日
- 2025年3月22日(土)
メールの設定により、ふるさと兼業からのメールが届かない場合がございます。
もしメールが届かない際は、迷惑メールフォルダをご確認くださいませ。
また、ドメイン指定受信を設定されている場合は「furusatokengyo.jp」を許可していただくようお願いいたします。
万が一2日以内に連絡がない場合は、お手数ですがふるさと兼業事務局([email protected])までお問い合わせいただきますよう、よろしくお願いいたします。
- プロジェクト開始までの流れ
-
募集は終了しました
担当地域パートナーからの推薦ポイント
- NPO法人G-net 棚瀬規子
- 㓛農支援会の農場に訪問したときに驚いたのが、施設園芸でありながら、オーガニック栽培から通常の栽培方法まで、自分たちが試してみたい栽培方法や農産物を多様に試せるところでした。研修生の方がおっしゃっていたことで大変印象的だったのは、「農場長である山口さんがなんでも試してもよい」と言ってくれるので、将来的な展望も踏まえていろいろ試すことができているという言葉でした。山口さんの応援やサポートも受けながら進められる場所であり、研修生の試行錯誤の多さではどこにも負けない施設だと思います。
-
お問い合わせ先 : [email protected]
/058-263-2162
団体の紹介
「農作物を栽培する力」「販売する力」「農業経営する力」が身につく実習で未来の農業の担い手を育成します。
団体情報
- 団体名
- 公益財団法人 㓛農支援会
- 代表者名
- 石黒 功
- 設立
- 2014年2月4日
- 事業内容
- ・農業の担い手の育成・確保に関する事業
・就農活動に対する支援に関する事業
・農業経営活動に対する支援に関する事業
・研修センターの管理運営
・当法人の目的を達成する為に必要な事業 - 業種
- 農業・サービス業
- WEB
- https://kounou-shienkai.jp/
- 住所
- 愛知県豊橋市西赤沢町万場261
- アクセス
- 農場住所:愛知県豊橋市西赤沢町万場261
アクセス:車 豊川ICより50分(国道151号線から国道23号線前芝IC経由、大崎ICで下り県道409号線へ)
公共交通機関 豊橋駅から渥美線 大清水駅を下車 タクシー10分
-
 お問い合わせ状況
お問い合わせ状況
-
2024年12月20日
山口県の企業様よりお問い合わせをいただきました。2024年11月05日
埼玉県の企業様よりお問い合わせをいただきました。2024年10月16日
滋賀県の企業様よりお問い合わせをいただきました。2024年10月01日
神奈川県の地方公共団体様よりお問い合わせをいただきました。2024年08月26日
長野県の企業様より、お問い合わせをいただきました。2024年08月06日
東京都の企業様より、お問い合わせをいただきました。2024年06月21日
東京都の企業様より、事業連携のお問い合わせをいただきました。2024年06月25日
宮城県の企業様より、お問い合わせをいただきました。2024年06月07日
石川県の企業様より、お問い合わせをいただきました。2024年04月08日
三重県の企業様より、お問い合わせをいただきました。2024年02月26日
宮城県の企業様より、お問い合わせをいただきました。2024年03月18日
徳島県の団体様よりお問い合わせをいただきました。2024年03月28日
東京都の企業様より、お問い合わせをいただきました。2024年03月14日
福岡県の地方公共団体様より、お問い合わせをいただきました。2024年03月06日
熊本県の企業様より、お問い合わせをいただきました。2024年03月04日
東京都の企業様より、お問い合わせをいただきました。2024年03月01日
北海道の地方公共団体様より、お問い合わせをいただきました。2024年02月28日
愛知県の企業様より、お問い合わせをいただきました。2024年02月19日
三重県の企業様より、お問い合わせをいただきました。2024年02月07日
東京都の企業様より、お問い合わせをいただきました。